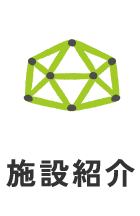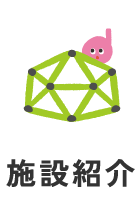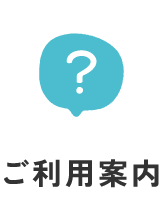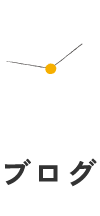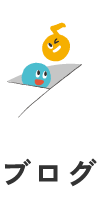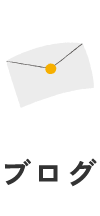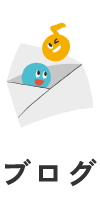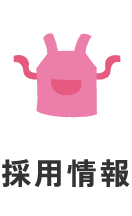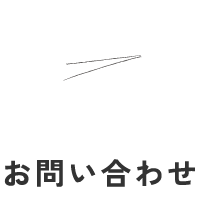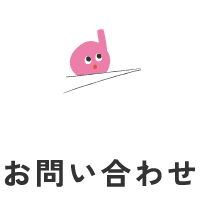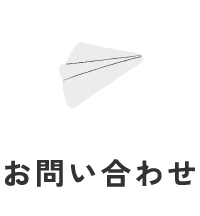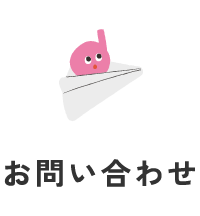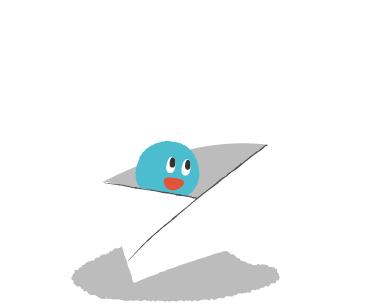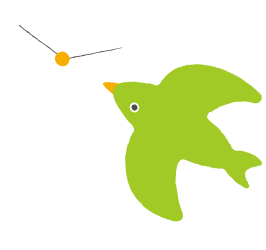こんにちは
ハッピープラス南堀江
児童発達支援管理責任者です
新学期が始まり、
あっという間に
1ヶ月が過ぎようとしています(^^)
新しい環境に、新しいお友達、
そして、新しい先生など、
少しずつ慣れてきたようですが、
たくさんの変化に、
少しお疲れぎみな様子も。。。
そんな時の解決策と言えば、
やっぱり、『いっぱい食べて、寝る!』
ですよね


今回は、そのなかの
『寝る=睡眠』について、
研修に参加してきましたので、
その内容をふまえて
お話ししていきますね

まずは、睡眠の効果について
考えていきましょう
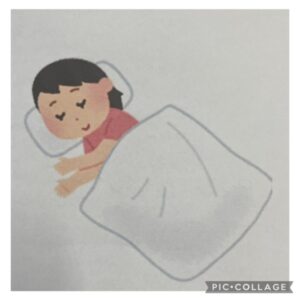
すぐに思いつくのは、
みなさんもご存知の通り、
疲労回復や、免疫力の維持、
ストレスの解消などが有名ですね!
しかし、なかには、
不眠症や、なかなか起きられないなど、
様々な症状を抱えている人も
少なくありません
また、発達障がいの特性にも、
同じような項目
(眠れない、起床困難、夜驚/夢遊病など)
があげられています。
それでは、若い人によくみられる、
『朝、なかなか起きられない場合』、
どうしたら、いいのでしょうか?
早寝早起きの
規則正しい生活をする?
アラームをいっぱいかけて、
起きられるようにする?

など、色々な方法があると思います。
一方で、おじいちゃん、おばあちゃん達は
どうでしょう?

早く寝て、早く起きるイメージですが、
夜中の2時に目を覚まして、
活動を始めてしまうなんてことも
あるようです

規則正しい生活が大事なのは
分かりますが、
これが、規則正しい生活に入るのか、
どうかは疑問です

そして、
夜中の2時に目を覚ますからと言って、
遅寝遅起きをすすめるのも、
どこか、違いますよね
色々と、難しいのですが、
『正しい睡眠』の基本的な考え方としては、
本人が快適に過ごしたり、
快適に寝たりすることができるよう、
“快適さ”を高めていくことが
大切なようです

また、人には”体内時計”という感覚が
そなわっており、
その感覚は人それぞれです。

ざっくり言うとすれば、
若者の体内時計は”ゆっくり”
高齢者の体内時計は”はやい”と、
研究では言われています。
なので、若者に朝寝坊が多くなる現象や、
高齢者の方が早起きになるのは、
ある意味、理にかなっているのです
ですが、社会生活において、
朝、起きられないことは、
困りますよね
具体的な解決策としては、
スモールステップで、
5分ずつ起きる時間を早めていくのも良し、
運動などの活動時間を増やし、
身体を疲れさせて、スムーズな入眠を
促していくのも良いかもしれません

『5分ずつ早く起きる』など、
目標が達成できた時には、
一緒に喜んだり、
その嬉しさを共有したりすることが
ポイントですよ
また、角度を少し変えた視点では、
太陽の光をあびること、
外に出ることなども、
体内時計がリセットされ、
快適な睡眠に繋がってきます(o^^o)

最後は、私たちが目にする、
“光(電気)”についても、
とても影響を受けることが
分かっていますので、触れていきますね ️
️
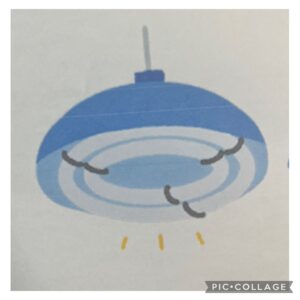
寝る前のスマホの使用は、
「避けた方がいい」と、よく耳にしますが、
“光(電気)”に注目すると、
『スマホの画面より
部屋のあかりの方が、明るい』
なんてことも !!
!!
スマホばかりに
目をとられがちになっていましたが、
“睡眠”を大きく捉えると、
寝室環境を改めることや、
そもそもの原因/背景を追求していくことも
重要ですね
ちなみに、寝室の電気は、
間接照明がオススメみたいですよ

このゴールデンウィークで
睡眠を見直し、暑い夏に向けて、
体調を整えていきましょう
それでは、少し早いですが、
楽しいお休みをお過ごしください

ハッピープラス南堀江では、
随時、見学・体験を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください
※株式会社公文教育研究会との
契約に基づき、
公文式学習導入施設として、
教材提供と学習指導サポートを
受けています。